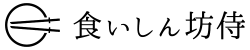今回の行き先は九州の福岡と佐賀の2県。太宰府天満宮や吉野ケ里遺跡を見学し、福岡の天神と佐賀で食事を楽しみました。
福岡県
太宰府天満宮

福岡では、まず太宰府天満宮を訪れました。学問の神様、菅原道真を祀った神社は全国に数多くありますが、三大天満宮は京都の北野天満宮と山口県の防府天満宮と、ここ太宰府天満宮です。京都の北野天満宮に参拝したことはありますが、太宰府天満宮は今回が初めてです。
9世紀終盤頃に朝廷で活躍した道真は藤原一門にうとまれ、九州太宰府の地に左遷されました。任地では政務も禁止され、俸給もなく生活は困窮を極め、2年後に不遇のうちに没してしまいました。菅原道真の死後、都やあちこちで疫病や災害が多発し、道真左遷に加担した貴族たちが次々と死んでしまったことが残された人々の恐怖を煽り、無念の道真の鎮魂のため祀られることになったのです。
埋葬のため菅原道真の遺体を乗せた牛車が道を行くと、途中どうしても牛が動かなくなり、その場所に埋葬したそうです。そして、その地に太宰府天満宮が建てられました。
菅原道真ゆかりの梅ヶ枝餅

太宰府天満宮での名物は「梅ヶ枝餅」です。餡が入った焼き餅で、駅から続く参道に立ち並ぶ土産物店の多くで売っています。餡を餅の薄皮で包み、鉄板で挟んで焼いたもので、表面には梅の図柄の焼印が押されています。
梅が枝餅の由来は諸説ありますが、ある老婆が困窮している道真公に梅の枝にさした餅を差し入れたことに始まるとも言われています。その後、江戸時代に全国からの太宰府天満宮参拝者のお土産として定着しました。
アメリカに住んでいた時に、和菓子の会で福岡出身の友人と一緒に梅が枝餅を作ったことを懐かしく思い出しつつ、店先の縁台に腰掛けて頂きました。もっちりとした生地に適度な甘さの餡、優しい味で美味しい!2〜3個はいけそうでした。
菅原道真の梅好きはよく知られています。「東風吹かば匂いよこせよ梅の花、主なしとて春を忘るな」と歌った道真公の心情を想像し、すでに梅の花の時期は終わっていましたが、天満宮にある梅の木を撫でて歩きました。
歴史ロマンを感じる九州国立博物館

太宰府天満宮を参拝をした後、九州国立博物館に行きました。九州国立博物館は日本4大国立博物館の一つです。九州の他は東京、京都そして奈良の3ヶ所です。他の3ヶ所の博物館が明治時代に開館したのに対し、九州国立博物館の開館は2005年と新しく、建物は現代風のガラス張りの外観をしています。中に入ると大きな吹き抜けのエントランスになっていてゆったりとした雰囲気です。
展示室は各時代ごとに分かれていて、日本文化が中国や朝鮮をはじめ、アジア諸地域の影響を受けながら発展してきた経緯が分かりやすく展示されていて見応えがありました。
どの時代も興味深く、素朴な土器に始まり、ヨーロッパとの交易でも扱われた華やかな美しい陶器・磁器・漆器に至る展示品は見事なものでした。
中国や朝鮮との交易に関係するものや元寇の時の遺品の中には、仏像も多く残されていて、当時の人々の願いのようなものがしのばれ、感慨深く時間が経つのを忘れてしまいました。
多種多様な展示品を鑑賞し、長い歴史にわたるアジア民族、日本民族双方の先人達の努力や行動力、そして夢とロマンに想いを馳せながら堪能しました。
福岡博多の絶品鯖料理

太宰府天満宮と九州国立博物館でしっかり歩き回ったため、ホテルに着く頃にはすっかりお腹も空いてきました。夕食は博多天神にあるお店です。人気店のようで席はほぼ満席で、唯一残っているカウンター席に案内されました。
まずビールを注文して「お品書き」に目を走らせました。目に飛び込んでくるのは「鯖」「サバ」という文字です。泳ぎ鯖刺し、炙り鯖刺し、胡麻鯖、鯖の自家製ぬか漬け(炙り生へシコ)、鯖の焼き味噌、鯖の燻製、焼き鯖のポテトサラダ、鯖コロッケ、鯖のチヂミ、焼鯖チャーハン、鯖のにぎり、胡麻鯖の茶漬けなど。
鯖は好物で、〆鯖、塩焼き、味噌煮、福井県小浜で有名な焼き鯖には馴染みがあります。しかし、「泳ぎ鯖刺し」という名に恥じない程の新鮮さを持つ鯖の刺身も、皮目を焼いた炙り鯖刺しも、白ごまで和えたゴマ鯖という刺身も、こんなに透明感のある鯖は生まれて初めてでした。
鯖の焼き味噌・焼鯖のポテトサラダ・鯖コロッケ・鯖のチヂミも鯖の臭みが全く感じられません。適度に脂が乗っているのでしょう、口の中にその旨みと甘みがふわーっと広がっていきました。
この店の名物である焼鯖チャーハンを、カウンターの端で板前さんが作っているのを眺めました。焼いた鯖を丁寧に何度も何度も細かく炒め、卵などと合わせていました。いざ食べてみると、細かく刻まれているために鯖自体は見えませんでした。しかし鯖の味はしっかりと感じられます。名物と書いてあるだけに、お店のプライドが感じられ、とっても美味しかったです。

対馬の穴子

鯖以外に、対馬の穴子を熱々の天ぷらにしたもの、煮穴子の卵焼き、浅漬け白菜の明太(めんたい)和え、茶豆のチーズ寄せもいただきました。
穴子はふるさと納税の返礼品としても人気らしく、大きくてぷっくらとしていました。地卵は平飼いされている鶏のもので、味も濃厚で名物の明太子(めんたいこ)とよく合っていました。
途中から日本酒に変え、福岡天神の夜を満喫しました。はるばる福岡まで来て良かった!とつくづく思いました。機会を作ってもう一度訪ねたいと思います。
佐賀県
古代の生活が垣間見える吉野ヶ里遺跡

翌朝、「吉野ヶ里遺跡」を見学しました。弥生時代700年間の歴史では我が国最大の遺跡ということで、何度か話題になっていたので、是非見学してみたいと思っていました。
JR吉野ヶ里公園駅から遺跡までは距離があるため、駅のそばの貸自転車センターで荷物を預け、自転車を借りて広い青空と見渡す限りの田園風景の中を「吉野ヶ里遺跡」に向かいました。
駐輪場に自転車を置き、広い入場門をくぐり、橋を渡ってしばらく歩くと、芝生の斜面に剥製のイノシシが置かれてあります。2000年前もこの地を駆けまわっていたのかと、思わず声をかけたくなります。
竪穴式住居のエリアには、王の家、妻の家、その娘夫婦の家など、支配者層の住まいも並んでいました。1メートル位ある階段を降りてゆくと、想像より広い土間があり、薄暗い中に炉・かまど、ベッドの跡がありました。
2000年前でも床でごろ寝をしていたのではない事に少し衝撃を受けました。ひんやりしていましたが、夏は涼しく、冬は炉で暖を取っていたようです。
当時の農具の他に青銅器や色あせた絹織物なども展示してありました。何でも、絹織物の「貝紫」という発色方法があったそうです。アカニシやイボニシなどの巻貝の内臓を糸や布に塗りつけ、日光に当てると化学反応で紫色に染まるとのことで、当時の手法に感心しました。
大きな丸太を組み合わせた高さ6~7メートル位の見張り台のような建物があったので、階段を登ってみると4畳程の広さがあり、集落全体を見渡せました。集落の周りには田んぼや畑らしき跡が広がっていて、東京ドーム球場の2~3倍程度ある感じでした。近くには川もあり、稲作が行われていたとの事に納得しました。
海外との交易品や日本各地から集まった品々を保存するための高床式の倉も多く立ち並び、当時の生活様式の高さが想像できました。百聞は一見にしかず、2000年前の古代の生活様式を垣間見ることができ、ロマンを感じました。
美しく強い有田焼

1900年のパリ万博で大変高い評価を受けた、有田焼きの深川製磁に立ち寄りました。デパートの食器売り場に行くような気持ちで訪れたものの、ここではとても手の出ないような高価なものが多く展示されていました。
すっかり目の保養をさせてもらった後、佐賀に来た記念にと、ホテルの近くのお店で手頃な茶碗を2個購入しました。
オレゴンで親しくしていた友人がロサンゼルスで日本食レストランを経営していた時、食器は有田焼きが多かったそうです。有田焼を好んだ理由は、頑丈で白磁の食器には透明感があり、食材を華やかに美味しそうに表現できるためのようです。アメリカから有田まで買い付けに行っていたそうで、食器を見ながらふとそんなことを思い出しました。
有田焼は江戸時代初頭に遡り、日本最古ともいわれる400年の歴史を持ちます。長い歴史の中で磨かれ、洗練されていき国内外で多くの人々に愛されているのでしょう。
佐賀の銘酒「鍋島」
この日の夕食も福岡と同じく和食居酒屋です。おしゃれな感じで若い人も多く、金曜日でもあり予約の7時には既に利用客で一杯でした。
通された席は昨日同様にカウンター席で幸運でした。天ぷら屋さんで一番良いとされる席は鍋の前と言われますが、居酒屋でも板前さんが料理をしている目の前に座るのが私は好きです。プロの料理人の手つきを間近で見ると臨場感を得られ食欲も盛り上がるというものです。
いつも通りビールを注文し、御品書きを見る前に板前さんに「イカはありますか?」と尋ねましたが、「今は入荷がありません」という返事でした。楽しみにしていたので残念でしたが、気を取り直し、刺身盛り合わせを注文しました。刺身の種類はカンパチ、ごまカンパチ、〆さば、カツオのたたき、サーモンの5種類。
刺身といえば日本酒です。お目当ての「鍋島 大吟醸」を注文しました。国内外で高く評価されていると聞いていましたが、そのフルーティーな味わいと爽やかな喉越しは絶品でした。追加、追加で結局3合頂きました。
有田の郷土料理「ごどうふ」

刺身の他には、脱皮したてのカニを甲羅ごと天ぷらにしたソフトシェルクラブの天ぷら、カニ味噌胡瓜、有明産真海老の唐揚げ、そしてご当地名物の「ごどうふ」を頂きました。
「ごどうふ」は注文してから板前さんが作ります。熱々のもっちもち、とろっとろの豆腐をゴマとワサビでいただきました。
「ごどうふ」という言葉を初めて耳にします。板前さんが作りながら説明してくれましたが、やはり有田の郷土料理だそうです。豆乳に葛を加えて固めたもので、卵豆腐やプリンのような食感で、とても美味しかったです。
再び福岡県
糸島の牡蠣小屋

最終日である旅行3日目の昼食は、福岡市内から西に位置する糸島の牡蠣小屋に行きました。電車内で、佐賀生まれの老婦人と親しくなり言葉を交わしました。彼女も旅が好きらしく、あちこち旅行した話をしました。食に関しては佐賀の日本酒と食材がどれ程美味しいか、と言うことを熱く語っていただき、こちらも前日夜に佐賀の料理と日本酒をたっぷり楽しんだので意気投合しました。
佐賀から唐津までは山間部と小さな盆地を走りますが、唐津で乗り換え筑肥線になると、車窓はひらけ玄界灘の海も見えます。糸島の『加布里駅』からタクシーで目的の牡蠣小屋に向かうと、店は漁港の前にあり、大きなビニールハウス造りで臨場感があります。
中では何組かの客が炭火の入ったコンロに乗せた網の上で魚貝類を焼いています。いわゆるバーベーキュー式のお店です。生ビールと魚貝類のセットを注文すると、カキ、サザエ、ホタテの貝類、イカ、エビそしてアナゴの魚類が運ばれてきました。
焼き始めてしばらくすると、固く入り口を閉ざしたサザエの口が熱さで耐えきれなくなったのか、大きな音と共に勢いよく破裂しました。最初何が起きたかよく分からず、ポカンとしていましたが、砕けた貝殻や周りの人たちの反応を見て何が起きたかが理解できました。店の人が飛んできて、手慣れた手付きで飛び散ったサザエの残骸を片付け、代わりの新しいサザエとタオルそして衣服の汚れ防止のビニールジャーパーを持って来てくれました。このようなことはよくあるらしいですが、旅の最後の食事が期せずして印象深い思い出となりました。
まとめ
今回は2泊3日と比較的短い旅程でしたが、福岡と佐賀の歴史、文化、食を存分に楽しむことができました。
九州北部は大陸に近く、特に航空機が無かった時代においては、日本の玄関のような役割があったと思います。遺跡や博物館や有田焼の見学で強く感じたのは、海外との歴史的、文化的なつながりでした。海外から入ってきた文化や先進の技術、産物が日本の暮らしに役立てられ、日本からも海外にも伝わるという環流です。
国内外の先人たちの知恵と努力に改めて感謝するとともに大いに刺激を受けました。
そして、博多の鯖はおいしい!
この記事を書いた人
- 青井 三郎
-
食いしん坊侍のスタッフ青井三郎。
戦後、奈良に生まれて大阪で育つ。6人兄弟の末っ子だったせいか、幼少の頃から食べることへの執着が強い食いしん坊だった。
野球少年だったが読書好きでもあり、日本や世界の文化や歴史に強い興味を持つ。大学時代には世界に触れたい欲求が高じ、1ドル360円の時代ではあったが、ヨーロッパ、南米、アフリカを3か月ほど巡る旅をした。結婚し東京で4人の子供を育て終えると、アメリカ西海岸のポートランドに10年間、美しい海と温暖な気候に惹かれて沖縄に3年間住む。
現在は、美食を求めて北海道へ移住。札幌を中心に食べ歩きを楽しんでいる。
最近の投稿
 列島美味紀行2026年1月18日アメリカのバーベキュー(BBQ)
列島美味紀行2026年1月18日アメリカのバーベキュー(BBQ) 列島美味紀行2025年2月25日食旅~福岡・佐賀編
列島美味紀行2025年2月25日食旅~福岡・佐賀編 列島美味紀行2024年10月9日四国それぞれの歴史・文化・食を巡る旅
列島美味紀行2024年10月9日四国それぞれの歴史・文化・食を巡る旅 列島美味紀行2023年12月6日オレゴンの食
列島美味紀行2023年12月6日オレゴンの食